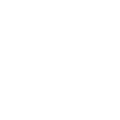1 従業員の着服、横領による損失の実体

経理や財務に深く関わる経理担当の従業員(経理部長、課長など)は、金額の多少にかかわらず、などの不正に手を染めやすい環境にあることは事実である。
その手口はいろいろあるだろう。直接、請求よりも多くの支払いをして、差額を抜き取る単純な手口から、仕入先や売先とグルで、架空外注費や水増し売上を請求させ、その差額を架空名義の会社や個人で振り込ませた後、そのお金を着服する手口、また新規の売先や売上紹介の見返りとして裏金を要求し、エビデンスなしで着服する手口など種々ある。
ところで、不正が発覚するのはそれが実行されてから、かなりの時間が経過してからのことが多い。
刑事告訴になれば、当然、その従業員に対して損害賠償請求が起こるのは当然であるが、もし有罪になれば、その人の社会的地位は決定的にダメージを受ける。そして、不幸なことに、会社が損害賠償請求しても、その債権が回収される可能性はほとんどないか、あっても、雀の涙ほどの返済を受けるのがやっとである。このように、被害者である法人は最悪の状況下にありながら、これに対する税務上の取り扱いは、非常に冷酷なものになるので、経営上、十分注意する必要があるだろう。
2 損害賠償請求権と益金算入時期
従業員の不正により金員が着服された場合、法人ではすでに費用(損金)計上されているから、その分利益は過小に計上され、所得も過小に申告されているわけであるから、税務当局としては法人税を含む課税徴収の機会を喪失したことになる。したがって、どこかの時点で利益を実現させなければならない(益金に算入しなければならない)。
<事案>
納税者はビル清掃、警備保安業務を営む法人甲社で、その従業員Aは、平成9年から平成16年にわたり、経理部課長の立場を悪用し、架空の外注経費の計上により、会社の金員を詐取した。甲社はこの事実に気づかなかったが、平成16年Y税務署の税務調査によって、その事実が発覚、判明した。
甲社は、平成16年5月、Aを懲戒解雇の上、7月に告訴し、Aは11月に詐欺罪で起訴され、平成17年6月実刑判決を受けた。また、甲社は平成16年9月に損害賠償請求をし、裁判所は同年10月に1億8千万円余の支払いを命ずる判決を下した。
3 Y税務署の処分内容
平成16年10月、Y税務署長は外注費の架空計上を理由として、平成9年9月期から平成
15年9月までの6事業年度について、法人税の更正処分及び重加算税の賦課処分決定をした。これは、詐取行為により損害を被った甲社は損害発生と同時に、法律上当然にAに対し損害賠償権を取得するのであるから、損害による損金計上と、損害賠償請求権の発生による益金は同時に両建計上され、結果として、架空外注費のみが損金から控除されるため、仮装行為に基づく過少申告になるとの考え方に基づく。この、損害発生と同時に益金計上すべきという考え方は、「同時両建説」といい、この事案ではY税務署長は一般的な「権利確定主義」によらず、「発生主義」の考え方を採用しているといえる。
つづく